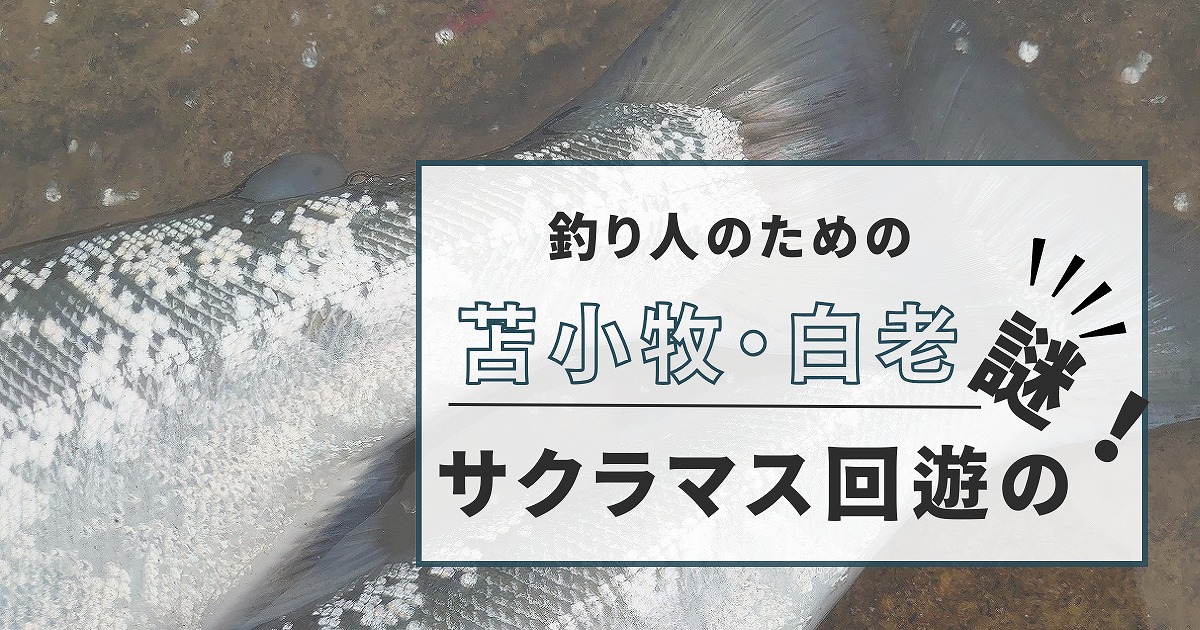はじめに:サクラマスの回遊パターンとその重要性
サクラマス(Oncorhynchus masou)は、サケ科に属する魚で、特に北海道近海での回遊が知られていますよね。苫小牧や白老沖は、1月、2月になるとサクラマスが特に多く回遊してくるエリアとして有名なのは皆さんご存知なはず!
では、なぜこれらの地域にサクラマスが集まるのでしょうか?その答えを知るためには、サクラマスの生態、環境要因、そして回遊メカニズムを深く掘り下げる必要がありそうです。
本記事では、苫小牧や白老沖にサクラマスが回遊する理由を、私の視点で考察しています。
サクラマスの生態と回遊行動

サクラマスは、他のサケ科の魚と同様に、降海して生活し、春に産卵のために河川に遡上します。この回遊行動にはいくつかの重要な要因がありますが、その中でも特に影響を与える要素として「水温」「餌となる魚の分布」「潮流」などが挙げられそうです。
水温とサクラマスの活動
サクラマスは冷水性の魚であり、水温に敏感なところがあるんです!回遊のタイミングや行動は、海水温の変化に大きく影響を受けます。特に、1月から2月にかけては、北海道周辺の海水温が低下し、サクラマスが好む水温(約5~10℃)の帯域が形成されます。それが、この時期に、サクラマスが餌を求めて回遊しやすくなる理由の一つです。
今回は苫小牧と白老にスポットを当てた記事になっていますが、実は津軽海峡にも沢山のサクラマスが回遊してくることが一般的にわかっています。遊漁船乗っている釣り人達は感覚でわかりますよね?
その、確信に迫るべく、さけ・ます資源管理センターニュース NO.14 2005年3月「北海道の河川に放流された標識サクラマスの海洋における回遊生態 眞山 紘・小野 郁夫・平澤 勝秋」を参考文献として読ませていただいたところ、1月以降に苫小牧沖や道南エリアに北海道内各河川のサクラマスが集中し、1月中旬には津軽海峡、以西地区海域の胆振で急増、2月に津軽海峡エリアで増え、大成町を主体に瀬棚、松前に分布、そして、3月には津軽海峡に滞在するサクラマスがピークになることが読んで私なりに解釈しました。
 シロ
シロ釣り人の感覚ではわかってはいるんだけど…



科学的にはちゃんと証明されているんだね♪
餌となる魚の分布
サクラマスの回遊は、その食物資源の分布にも密接に関連しているのは言わなくてもなんとなくわかりますよね?サクラマスは小魚や甲殻類を捕食するため、餌となる魚群の存在は非常に重要なんです。苫小牧や白老沖は、これらの餌となる魚が豊富に生息しているエリアであり、特に小魚の回遊が活発な冬の時期にサクラマスが集まるワケです。回遊してくる理由は沢山あると思いますが、理由の一つとして、餌を求めサクラマスがこのエリアに回遊してくる。と言うのがわかっています。
学術的な視点から見る回遊のメカニズム
サクラマスの回遊行動は、単なる偶然ではなく、遺伝的な要因や生理的な反応によって精密にコントロールされています。以下では、サクラマスの回遊メカニズムに関する学術的な視点を見ていきます。
ホルモンと生理的な反応
回遊行動には、ホルモンの影響も重要です。サクラマスは、繁殖期が近づくと体内で「メラトニン」や「コルチゾール」などのホルモンが分泌され、これが回遊の行動を促進します。特に、光の周期(昼夜の長さ)によってホルモン分泌が調整されるため、季節的な回遊が可能となるのです!
実はコレ、人間にも当てはまることがあり、体内時計や生体のリズムはサクラマスだけと言うわけではなさそうですね。
・概日リズムの調節や環境の光条件への応答、さらにストレス応答については人間も魚も共通するところはありそうです!
栄養の蓄積と体調の管理
サクラマスが苫小牧や白老沖に回遊してくるのは、冬の間に体力を蓄えるためでもあります。特に寒冷水域では、新陳代謝が低下し、体が省エネルギー状態になるため、効率的に餌を摂取することが重要です。サクラマスは、この時期に食物を求めて回遊し、エネルギーを蓄えて産卵に備えます。
苫小牧・白老沖の水域がサクラマスに与える影響
苫小牧や白老沖は、サクラマスにとって非常に適した環境が揃っている場所です。そして、この地域の水域には、サクラマスの生態にとって重要な要素が豊富に揃っています。
また、苫小牧・白老、そして津軽海峡には前に書いたように、この時期になると、全道各地からサクラマスが集まってきます。ここで徐々に大きく育ったサクラマスは春になると全道各地に帰って行くと言うメカニズムになっているようです。
海流と水温の相関
苫小牧・白老エリアは、日高方面から来る海流をメインに、室蘭・噴火湾付近でクルリと海流が回るような場所に位置してますよね。この湾のような地形もあり、冬期のサクラマスにとっては理想的な水温帯が形成されます。特に冬季は水温が安定しており、サクラマスが活動しやすい環境となります。
栄養豊富な海域
苫小牧・白老沖周辺は、プランクトンや小魚が豊富な地域であり、これらの餌となる生物がサクラマスを引き寄せます。特に、冬季における魚群の回遊パターンは、サクラマスの捕食行動にとって重要ですね。
まとめ
苫小牧や白老沖にサクラマスが回遊してくる理由は、単に水温や餌の豊富さにとどまらず、ホルモン、さらには栄養源としての魚群の存在など、複合的な要因が関与していると考えています。
サクラマスの回遊行動は非常に精密で、自然環境における多くの変化に応じて行動していることがわかります。
だって、ちゃんと生まれ育った川に戻る。これ、この釣りをする方なら大抵知っていることかと思いますが、本当に精密機械のような魚です。
これらの要因を知ることで、サクラマスの回遊メカニズムについてより深く理解できるとともに、釣りのタイミングや場所をより効果的に選ぶことができるようになるでしょう!
ただ、私わからないことあるんですよ。
遊漁船に乗ると、日によって水深100mみたいなところマダラと一緒にいたり、別の日は水面跳ねてたり。あの差は何故なのか未だにわかりません(^^;
サクラマスってホント不思議な魚ですね。
参考文献 さけ・ます資源管理センターニュース NO.14 2005年3月「北海道の河川に放流された標識サクラマスの海洋における回遊生態 眞山 紘・小野 郁夫・平澤 勝秋」