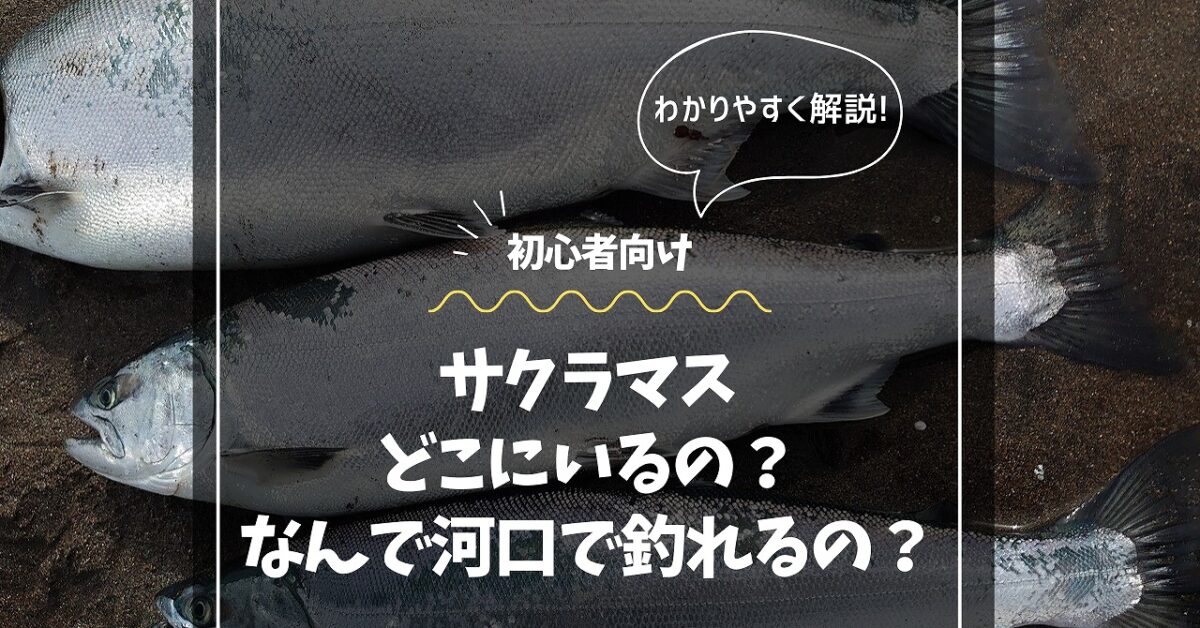「サクラマスって川に帰ってくる魚なんでしょ?だったら河口にいるのって当たり前じゃないの?」
うん、それも一理あるですが……実はそれだけじゃないんです!
釣り人としては「どこで釣れるか」が超大事ですよね。今回はその謎を解明すべく、論文を探していたところ、非常に興味深い研究論文を見つけたので、それを根拠に「サクラマスがなんで河口付近にいるのか?」を、できるだけわかりやすくお伝えします!
サクラマスの「母川回帰」ってなに?
サクラマスは、生まれた川に戻ってくる“帰省好き”な魚。
この習性のことを「母川回帰(ぼせんかいき)」っていいます。ちょっと難しい言葉だけど、要は「ふるさとに帰ってくる」ってことですね!
 レイン
レイン生まれた川大好きっす!
これ、実はすごく正確で、「ピンポイントで自分が生まれた川を探し当てる」能力があるらしいんです。魚ってすごいですね!
「河口で釣れる=母川に帰ってる」だけじゃ説明できない理由
でもね、「川に帰ってくる途中で釣れるんでしょ?」って思うかもしれないけど、北海道だと3月とかって、まだ遡上してないサクラマスも多い時期なんですよ。
それなのに河口でよく釣れる…。
ってことは、もしかして、川に入る前の“何か”をしてるときに釣れてるのかも!?
ってことで、ここからはその「何か」を探っていきましょう!
サクラマスはなぜ河口で釣れるのか?その理由を科学的に解説!
「サクラマスって川に帰ってくる魚ですよね?だったら河口で釣れるのは当たり前じゃん!」
――なんて思うかもしれませんが、実はそれだけじゃ説明できないんです。
実際、私が釣った67センチのサクラマス(某ダービー優勝魚!)も、まさに河口近くでヒットしました。でもその時期、川には全然サクラマスが入っていなかったんですよね。


3月頃って、まだ川に上る前のサクラマスもたくさんいて(北海道のサクラマスは殆ど海にいる)、そのタイミングでも河口で釣れることがあるんです。
じゃあなぜ河口なの?そのヒミツを、科学の視点からちょっと深掘りしてみましょう!
サクラマスの回遊行動に関する研究論文を読み解く
引用した論文と研究者について
今回参考にしたのは、北海道大学の上田宏(うえだ ひろし)氏達が書いた論文です。
- 『サケの感覚機能と母川回帰』上田宏 2007
- 『サケ科魚類の母川回帰機構:視覚と嗅覚の役割』上田弘 帰山雅秀 栗原堅三 山内晧平 1996
という2つ。これがかなり興味深い内容なんです!
サクラマスがどうやって自分の川を見つけるのか、におい?目?それとも方向感覚?というのを、本気で科学的に調べてくれているんですよ。
視覚・嗅覚・磁気感覚がサクラマスの行動に与える影響
この研究では、サクラマスのおもしろい実験をしています。
たとえば――
- 鼻にワセリンを塗って「におい」を感じさせなくする
- 目の網膜をいじって「視力」を奪う
- 頭に強力な磁石をつけて「磁気感覚」を狂わせる
えぇ〜!? って感じですよね。でも、これによってどの感覚がどんなふうに行動に関係してるかが、よくわかるんです。
視覚・嗅覚を奪われたサクラマスの行動パターンとは?
たとえばこんな結果が出ていました。
- 鼻をふさがれたサクラマス:岸から離れてしまう
- 視力を奪われたサクラマス:進む方向がフラフラ(迷走)しちゃう
つまり、サクラマスは岸沿いを泳ぎながら、目と鼻を使って川を探しているということなんですね!
これってまさに、河口付近でサクラマスがよく釣れる理由につながりそうじゃないですか?
なぜサクラマスは岸沿いを回遊するのか?
岸沿いに回遊することで母川を探している
先ほどの研究では、サクラマスが「目」と「鼻」を使って川を探していることがわかりましたよね。
で、面白い実験があるんです!
洞爺湖の実験所から、ちょっと離れた場所にサクラマスを放したところ、なんと彼らは必ず岸沿いに移動していたんです。
しかも川の流れ込みがある場所では、「あっ、ここなんか違う!」って感じで立ち止まるんですよ。そして、またスススーッと動き出す。
まるで、「ここ、うちの川じゃないな〜」ってチェックしてるみたいですなっ!
流入河川があると必ず立ち止まる理由


この行動からわかるのは、サクラマスは湖の真ん中とかを適当に泳いでいるわけじゃなくて、岸沿いをちゃんとたどって、川を探しているってこと。
さらに、こんな記録もあります👇
「5km離れた湖の真ん中に放されたサクラマスは、まっすぐ生まれた場所には戻れず、逆方向の岸を目指して迷った」
(引用:サケ科魚類の母川回帰機構:視覚と嗅覚の役割 上田弘 帰山雅秀 栗原堅三 山内晧平 1996)
つまり、サクラマスってヒメマス(方向感覚バッチリな仲間)みたいに「GPSみたいな感覚」でピンポイントに行くんじゃなくて、
- 目で見ながら
- においを嗅ぎながら
- 岸を伝って
という“地道な川探しの旅”をしてることが予想されます。
この「岸沿いを移動して川を探す」って行動が、まさに河口近くでよく釣れる理由のカギなんですな!
次のセクションでは、その決定的な要素「におい(アミノ酸)」について見ていきますね!
サクラマスがニオイで川を識別しているという事実


河川水中のアミノ酸を感知している可能性
サクラマスは、自分が生まれた川を“におい”で覚えていて、それを頼りに帰ってくるってお話、ご存知ですか?
実はその「におい」の正体は、川の水に含まれているアミノ酸なんじゃないかと言われています。
つまりサクラマスは、
「お、なんか懐かしいニオイがするぞ…」
って感じで、川の近くまでくるとピタッと止まるんです。
このアミノ酸のにおいは、川から少し離れた場所じゃあんまり届かないみたい。だから、川のすぐ近く=河口付近にまで来ないと気づけないってこと!
ある程度近づかないとニオイがわからない理由
さっきの論文にも、こんなことが書いてありました👇
「ヒメマスとサクラマスは、ある程度河口に近づかなければ湖水と河川水を認識できない」
(引用:サケの感覚機能と母川回帰 上田宏 2007)
つまり、サクラマスはある程度岸沿いを移動してきて、「お、この川のにおい知ってるぞ…!」と感じたら、やっとそこが生まれた川かもって判断するんですね。
これはもう、“魚界の迷子防止タグ”みたいなもんですね(笑)
この「においをたどる行動」こそ、サクラマスが河口付近に集まりやすい=釣れやすい理由のひとつと考えられます!
さあ次は、いよいよまとめに近づいてきました!
👇次のセクションでは「じゃあ釣れてる時って、どんな状態なの?」ってところを楽しく掘っていきます♪
河口でサクラマスが釣れるメカニズムの仮説
川を探している途中でルアーに反応している?
ここまでの話をまとめると、サクラマスが河口近くで釣れる理由って、
●岸沿いを移動していて
●においをたどりながら
●自分の川を探してウロウロしている
っていう、そんな“川探しの旅”の途中にあるみたいなんです!
つまり、サクラマスは「ここが母川かな?」と立ち止まって確認しているときに、目の前をキラリと光るルアーが通って……思わずパクリ!みたいな感じで釣れることがあるってこと!
冷静に考えると、すっごいタイミングですよね(笑)
母川回帰行動と釣果のタイミングの関係
特に3月〜5月のように、まだ本格的な遡上(川に入る)シーズン前は、サクラマスが「川に入るかどうか迷っているタイミング」でもあるんです。
そんな時に河口付近をウロウロしているので、
釣り人がそこにルアーを投げてみたら、タイミング次第でドカンとヒット!
ということが起きるわけですね!
なので、「釣れる場所を探す=母川回帰の行動を読む」っていう視点は、けっこう大事なのかもしれません!
海サクラマスにも通用する?淡水での研究結果を応用するには
海との違い
ここまで紹介したデータは、湖(洞爺湖)での実験結果なので、「じゃあ、海のサクラマスでも同じなの?」ってところは、私はわかりません。
海は広くて流れも複雑なので、湖とは違う動きをしているかもしれませんし、潮の流れとか水温も関係してくるかもしれません。
でも!
サクラマスの本質的な習性、「岸沿いを泳ぎながらにおいで川を探す」って行動は、海でもきっと変わらないはずと私は思っています。



サクラマスはめっちゃ鼻が良いのですよ!



川ごとのにおいをかぎ分けれるだなんてスゴイ!
それでもポイント選びのヒントにはなる
だからこそ、この習性を知っていると、「なんとなく投げてる」より「ここなら釣れるかも!」って狙える場所が増えるんです!
例えば…
- 河口近くの浅場
- 岸沿いで流れ込みのあるポイント
- 何かにおいを発していそうな場所(川・用水路・湧き水など)
こういう場所を「もしかして立ち止まってるかも?」ってイメージしながら投げてみると、釣果が変わるかもしれませんよ!
まとめ:サクラマスの行動を知れば釣果アップにつながる!
というわけで、ここまで読んでくださってありがとうございます!
今回の内容をざっくりまとめると――
- サクラマスは岸沿いを移動しながら、
- におい(アミノ酸)で自分の川を探していて、
- その途中で河口に立ち寄る
- そして、たまたま通ったルアーに反応することがある!
つまり、釣れる理由にはちゃんとサクラマスの“生き物としての習性”が関係しているってことなんですね。
難しい話もあったけど、こうやって知っておくと、釣り場選びもグッと楽しくなるし、想像しながら釣るのってめちゃくちゃワクワクしますよね!
それではみなさん、サクラマスとの駆け引きを楽しみながら、思いっきり釣りを楽しんでください!